第2回日中財政社会学シンポジウム開催報告
- jcpublicfinance
- 9月16日
- 読了時間: 6分
2025年8月17日から22日にかけて、第2回日中財政社会学シンポジウム「中日財政社会学研究前沿」が東京経済大学を中心に開催されました。日中財政研究会は、東京経済大学、専修大学と共に本シンポジウムの企画・運営に参画し、昨年浙江財経大学で開催された第1回に続く、記念すべき第2回大会となりました。
本シンポジウムには、中国から浙江財経大学、中国人民大学、浙江大学、上海行政学院、日本から東京経済大学、専修大学、慶應義塾大学、東北大学、明治大学などの大学・研究機関から多くの研究者と大学院生が参加しました。

シンポジウムのプログラム
今回のシンポジウムは特徴的な二段階構成で実施されました。第1日目の8月18日には、東京経済大学において少人数による閉門会議形式の専門学術報告会が開催され、各研究者が時間をかけて自身の研究を発表し、濃密な議論を展開しました。
明治大学の倉地真太郎准教授による「財政社会学における国際比較の可能性」では、財政社会学の方法論について新たな視座が提示されました。浙江財経大学の付文林教授は「人口高齢化と中国地域間財政配分関係の再構築」において、中国が直面する急速な高齢化が地方財政に与える影響と、それに対応するための財政制度改革の必要性を詳細なデータと共に論じました。東北大学の佐々木伯朗教授は「『租税の財政社会学』における介護保険制度構築の日独比較」を通じて、福祉国家における財政制度の役割について比較制度論的アプローチから分析しました。

シンポジウムでの活発な議論
8月19日の公開シンポジウムでは、東京経済大学の岡本英男学長が開会挨拶で、気候変動、福祉負担、国際紛争などの重大な現実問題の解決に向けて、財政社会学的アプローチの重要性と日中学者の協力強化の必要性を強調しました。

基調講演では、浙江財経大学の李永友教授が「雍正時期の税制改革と社会衝突」というテーマで、清朝雍正帝時代(1723-1735年)に実施された「摊丁入亩」改革を詳細に分析しました。この改革は人頭税を土地税に統合するという画期的なもので、現代中国の税制改革にも通じる示唆を含んでいるという指摘は、多くの参加者の関心を集めました。

慶應義塾大学の金子勝名誉教授による「シュンペーターを読み直す」では、ヨーゼフ・シュンペーターの財政社会学理論を現代的文脈で再解釈し、イノベーションと財政制度の関係について新たな理論的枠組みを提示しました。東京経済大学の佐藤一光教授は「財政社会学とは何か:現代財政問題を読み解く」において、財政社会学の基本概念を整理しつつ、日本の財政問題への適用可能性を論じました。

中国人民大学の呂冰洋教授による「財政の文化的基礎」は、儒教文化圏における財政制度の特徴を文化論的視点から分析した意欲的な報告でした。税に対する国民意識、政府への信頼、公共性の概念などが、東アジアと西洋でどのように異なり、それが財政制度にどう反映されているかという問題提起は、会場で熱い議論を呼びました。

専修大学の徐一睿教授は「平和と財政―戦争財政国家から民主財政国家への変遷」において、戦後日本の財政制度の変遷を「戦争財政国家」から「民主財政国家」への転換という視角から分析し、現代中国の財政改革への示唆を提示しました。上海行政学院の劉志広教授による「中国財政社会学の新進展」では、中国における財政社会学研究の最新動向が紹介され、特に地方政府の行動分析における新たなアプローチが注目を集めました。
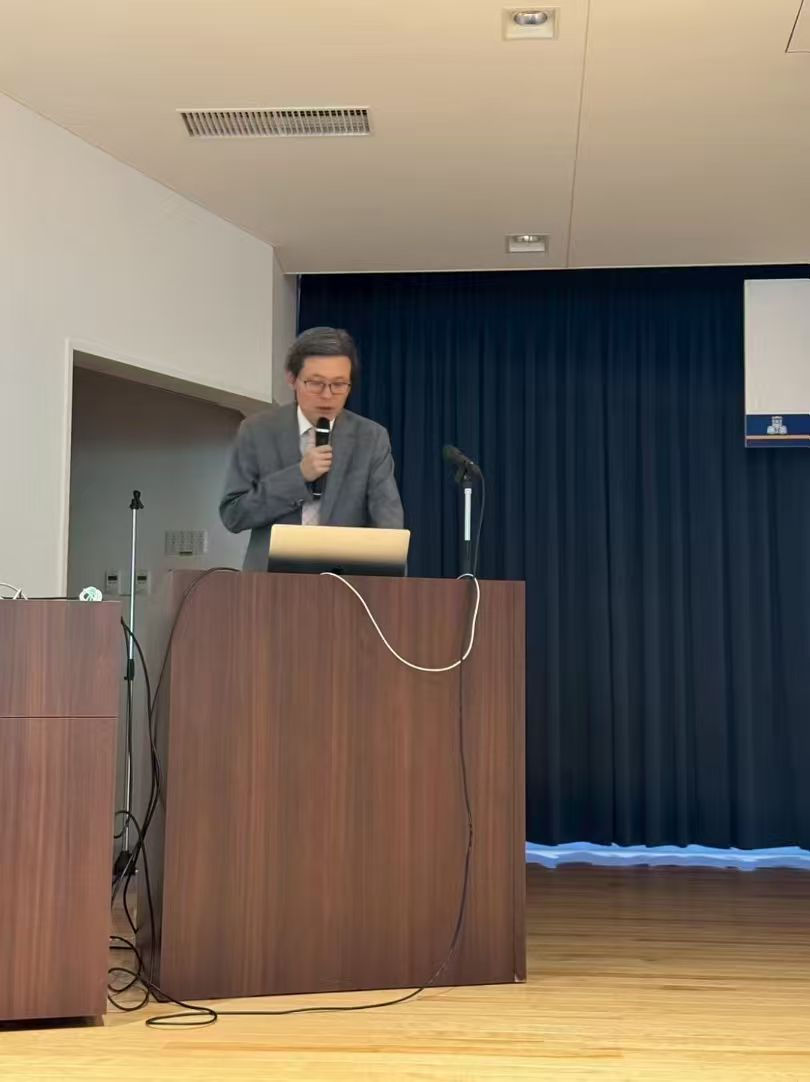
8月20日から21日にかけて専修大学で行われた二国間交流セッションでは、より実務的な協議が行われました。浙江財経大学の「財税基礎理論と政策研究」チームと専修大学の徐一睿教授チームとの間で、財政社会学教材の共同開発について具体的な計画が立てられました。また、大学院生の相互派遣プログラムについても、期間、人数、研究テーマなどの詳細が検討されました。
特に重要な成果は、中国国家自然科学基金委員会(NSFC)と日本学術振興会(JSPS)が共同で実施する「中日合作交流与双辺研討会」プロジェクトへの共同申請が決定されたことです。これにより、両国の公的研究資金による支援を受けた本格的な共同研究が期待されます。

第3回シンポジウムは再び中国での開催が予定されており、この重要な学術交流プラットフォームの継続性が確保されました。参加者からは「これはアジア財政社会学研究の新たな起点となる」「定期的な交流メカニズムにより、日中学者間の密接な学術的つながりが維持される」といった声が上がり、今後への期待が表明されました。
日中財政研究会としては、このシンポジウムで築かれた人的ネットワークと研究協力の枠組みを基盤として、今後も両国の財政学界をつなぐ架け橋としての役割を果たしていきます。オンラインセミナーの定期開催、共同研究プロジェクトの推進、若手研究者の交流プログラムなど、多層的な活動を展開し、アジアにおける財政社会学研究の発展に貢献してまいります。
今回のシンポジウムの成功は、参加・支援してくださったすべての関係者の協力の賜物です。日中両国の学者による知恵の結晶とも言える活発な意見交換は、この分野に新たな活力を注入し、今後の研究発展への道筋を示すものとなりました。
謝辞
最後になりましたが、今回のシンポジウムの成功は、多くの方々のご協力なくしては実現できませんでした。
まず、遠路はるばる中国から来日してくださった李永友教授、呂冰洋教授、付文林教授、魯建坤教授、高琳教授、劉志広教授、張暁鳴研究員をはじめとする中国の研究者の皆様に、心より感謝申し上げます。長時間のフライトと慣れない環境にもかかわらず、精力的に研究発表と討論に参加してくださったことは、本シンポジウムの成功の最大の要因でした。
日本側からも、金子勝名誉教授、佐藤一光教授、佐々木伯朗教授、倉地真太郎准教授など、ご多忙の中を縫って参加してくださった先生方に深く御礼申し上げます。また、会場を提供してくださった東京経済大学の佐藤一光教授、岡本英男学長をはじめとする関係者の皆様、運営にご協力いただいた専修大学の皆様にも感謝いたします。
そして、両国から参加してくださった大学院生の皆さんの熱意ある参加が、シンポジウムに若々しい活力をもたらしました。皆さんの積極的な質問と議論への参加は、財政社会学の未来への希望を感じさせるものでした。
日中財政研究会は、今後もこのような貴重な学術交流の機会を大切にし、両国の研究者の皆様と共に、財政社会学研究の発展に向けて歩んでまいります。改めて、すべての参加者・協力者の皆様に心より感謝申し上げます。




コメント